
2011年、家庭教師派遣事業を展開する教育系グループの営業責任者に就任し、3年間従事。2015年に教育ベンチャーを起業して以来、一貫して小・中学生向けICT教材の企画・開発に携わり、無学年式のオンライン学習教材「サブスタ」を開発。
また、昨今不登校生が増え続ける中、全国の通信制高校と連携し、サブスタを通じて出席扱い制度普及の活動を行っている。

正しく学ぶ方法や成績の伸ばし方、
不登校に悩まれている方のための
情報を発信しています。
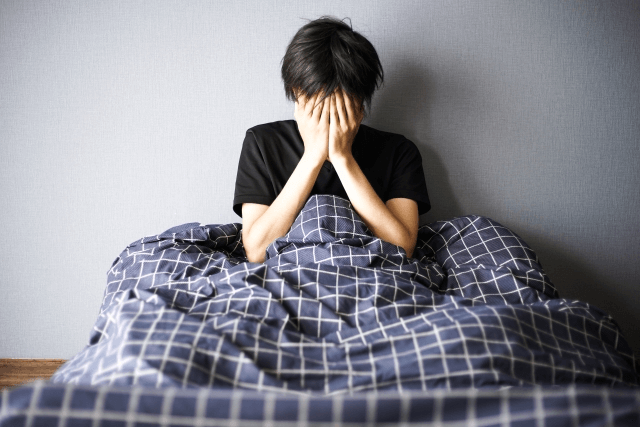
不登校になると、昼夜逆転生活を送ってしまうお子さまは珍しくありません。昼夜逆転はお子さまの身体の負担になりますし、不登校後の生活を思うと「このままでよいのか」と不安になってしまいますよね。
そこで今回は、不登校中に昼夜逆転生活になってしまう原因と、保護者様ができる対応方法についてご紹介します。
もくじ

不登校中のお子さまは、昼夜逆転生活を送ることが多いとされています。特に不登校初期にはそれが顕著で、「不登校初期は昼夜逆転生活が普通」と述べる児童精神科医も存在するほどです。
とはいえ、保護者様は「昼夜逆転なんて身体に悪いのではないか?」「昼夜逆転生活で将来大丈夫なんだろうか?」と不安に感じてしまいますよね。
そこでまずは、不登校中に昼夜逆転生活となる主な原因を4つご紹介します。
不登校中に昼夜逆転する原因の1つ目は、「生活の変化によるストレス」です。
お子さまが望んで不登校になったわけではないとはいえ、不登校になるとこれまで1日の大部分を占めていた「学校」という場所での生活がなくなり、家庭での時間がメインになりますよね。このような急激な環境の変化は、お子さまに無意識のうちにストレスを与えてしまいます。
また、不登校になったことへの罪悪感や不安から、本来眠るべき夜間に眠れなくなってしまうこともあります。人生経験豊富な大人でも、思い悩んで眠れなくなってしまうことはありますよね。まだまだ未熟なお子さまであればそれは尚更でしょう。
日中に起きていると「本当だったら今頃学校に行っていないといけない時間なのに…」と自分を責めてしまい、だんだんと明るい時間に起きていることに恐怖を抱くようになってしまうケースもあります。
お子さまにも自覚できていないストレスによって、昼夜逆転に繋がってしまうことがあります。
不登校中に昼夜逆転する原因の2つ目は、「不登校による生活リズムの乱れ」です。
学校生活を送る中では、朝起きる時間や食事の時間など、時計を意識しながら規則正しい生活を送る必要がありますよね。決められた時間通りに過ごせるよう、保護者様や学校の先生によって管理もなされていますし、集団生活の中で自然とそれが当たり前になっているものです。
しかし不登校で自宅で過ごすようになると、これらの規律が一切なくなってしまいます。起床や食事などが、良くも悪くも自分のタイミングで行えてしまうのです。
こうした制限や縛りの無さによってだんだんと生活リズムが乱れていくと、昼夜逆転に繋がりやすくなります。
不登校中に昼夜逆転する原因の3つ目は、「スマホ・ゲームなどへの依存」です。
スマホでSNSをしたりゲームをしたりすることが好きなお子さまは多いですよね。しかし、規則正しく学校に登校する生活の中では、それらに費やせる時間は限られているため、なかなか寝る間を惜しんでまで熱中するという生活にはならないはずです。
しかし前項でご紹介したように、不登校になると時間の縛りがありません。自由に使える時間も多く、ついついスマホやゲームにのめり込んでしまいがちです。
夜間のスマホやゲームの利用を禁止しているご家庭であれば話は別ですが、そうでない場合、時間を忘れて夢中になってしまうことも珍しくありません。
特にゲームといった「お子さまの好きなこと」であれば、いくらでも続けられてしまいますよね。また、好きなことをしている間は不登校という問題を忘れることができるため、「現実逃避」としてスマホ・ゲームに没頭してしまうお子さまもいます。
不登校中のゲーム依存に関しては、下手に禁止したりすると親子関係悪化を招く原因となりますので注意が必要です。以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
▶不登校中にゲーム依存になりやすい理由は?依存症を防ぐ対処法を解説します
不登校中に昼夜逆転する原因の4つ目は、「心身の病気の可能性」です。
不登校中の昼夜逆転生活の背景には、お子さまご本人の意識ではどうにもならない「病気」が潜んでいるケースもあります。
思春期のお子さまに起こりやすい代表的な病気は、「起立性調節障害」。起立性調節障害とは、自律神経系の以上によって循環器系の調節がうまく機能しなくなる疾患です。朝起きられない、夜寝つけないといった症状のほか、立ちくらみ・めまい・ふらつき、頭痛、気分不良、倦怠感といった症状が起こることもあり、昼夜逆転生活になりやすいことが特徴です。
症状の程度や期間はお子さまによってさまざまですが、長くても2~3年程度で落ち着き、社会復帰が目指せると言われています。
このように、病気によって昼夜逆転生活に陥ってしまうケースもあります。お子さまや保護者様の意識・努力によっても一向に状況が改善されない場合、病気の可能性を疑ってみるのも有効でしょう。病気と分かれば。お子さまが「朝起きられないのは怠けのせい」といったように自分を責める必要もなくなります。
起立性調節障害については、下記の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
▶不登校の原因は起立性調節障害?関連性と親ができるサポートについて

昼夜逆転生活がしばらく続くと、睡眠不足による体調の悪化やメンタルの不調が見られます。不登校がきっかけで昼夜逆転生活になってしまっているお子さまは、誰もが直したいと考えているでしょう。
ここではお子さま自身が昼夜逆転生活を直すためにできることを解説します。
寝る前にスマホの画面を見ると、ブルーライトの影響によってメラトニンという睡眠を促すはたらきがあるホルモンの分泌が抑制されてしまい、睡眠の質が悪くなります。また、体内時計の調節が乱れてしまい、睡眠のリズムが崩れてしまいます。
特にオンラインゲームなど、人とコミュニケーションを取りながら行う対戦型のゲームを寝る直前まで楽しんでしまうと、さらに頭が活性化してしまい寝れなくなってしまいますので注意が必要です。
メラトニンが分泌されるのは就寝する1~2時間前と言われているので、寝る2時間前にはスマホやパソコンの画面を見るのをやめましょう。
昼夜逆転になることで慢性的な睡眠不足になってしまいます。お昼ご飯を食べたあと、消化が進んだ15~16時ごろになると眠くなるのではないでしょうか。
だらだらと昼寝してしまうと夜眠れなくなるのは当たり前です。ここは昼寝したい気持ちをグッとこらえて我慢してください。どうしても我慢できない場合は15時までに20~30分にしましょう。
自宅にずっといることで運動不足になってしまうと、体力を消費しない状態が続いてしまいます。一日30分~1時間程度ウォーキングができると、運動不足が少しでも解消されるでしょう。
小・中学校の通学時間が終わる10時~12時あたりの時間になると、周りの目を気にせずウォーキングできるのでお勧めです。昼間の時間が難しければ、保護者様と一緒に夜の時間に行うこともよいと思います。
また、適度に体を動かすことで、成長ホルモンが分泌され深い睡眠を促してくれます。まずは短い時間でもよいので体を動かすことを習慣化できるようがんばってみてください。
不登校中に気軽に始められる運動不足解消法については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。
▶不登校による運動不足を解消するには?体力作りにはストレッチが効果的!

ここまでご紹介したように、不登校中の昼夜逆転生活にはさまざまな原因が考えられますが、保護者様はどのような態度でお子さまに接し、関わっていけばよいのか悩まれてしまいますよね。
そこで、親子ともに無理なく昼夜逆転を改善していくための対応方法についてご紹介します。
お子さまの昼夜逆転について保護者様が悩み、不安に感じてしまうのは当然のことと言えます。
しかし、そのような保護者様の焦りや「生活を改めなさい」といった指摘は、不登校で心が弱っているお子さまにますます負担をかけることになります。焦りをグッと堪えて見守ることで、まずはお子さまにとって家庭が安心できる場所になることに専念しましょう。
保護者様は、不登校中の昼夜逆転を改善しようとされるかもしれませんね。しかし実は、「昼夜逆転で困っているのは誰なのか?」と考えてみると、それは「お子さまではなく保護者様の方だった」というケースは非常に多いのです。
たとえば、お子さまの昼夜逆転生活によってその他の家族の食事や入浴時間などに支障が出てくると困ってしまいますよね。そのような困り感からお子さまを正そうとされる保護者様は多いのですが、お子さまは既に昼夜逆転が良くないことだと自覚し、思い悩んでいる場合もあります。
保護者様はそれに追い打ちをかけるのではなく、お子さまの気持ちを尊重し、悩みを共有しながら「見方だよ」という態度で関われるとよいですね。保護者様の接し方によってお子さまの負担が軽くなると、特別なことはしなくても拍子抜けするほど事態が好転することもあります。
お子さまが家庭で休息を十分に得られてきたら、少しずつ昼夜逆転生活を改善する試みにトライしてもよいでしょう。このとき重要なのは、保護者様とお子さまが同じ目標を持ち、共有できているということ。お子さまの気持ちを汲み取れていなければ、改善は難しくなってしまいます。
具体的には、一緒に食事をする、お子さまの興味がありそうな場所に出かけてみるなど、日中に“些細な”予定を入れてみることから始められるとよいですね。あくまでお子さまが主体となって、保護者様はサポートに徹する形での活動をおすすめします。
不登校対応の基本は「スモールステップ」です。お子さまのペースで無理なく進めていきましょう。
スモールステップでの不登校対応については、以下の記事でもご紹介しています。
▶不登校にはどう対応する?再登校するまでに親子でできる対応方法をご紹介

今回は、不登校中の昼夜逆転生活の原因とその対応方法についてご紹介しました。
特に不登校初期によくみられる、昼夜逆転。無理のない対応方法、ペースで少しずつ改善することを目指していきましょう。

こんなお悩みありませんか?
「不登校が続いて勉強の遅れが心配…」
「勉強をどこから始めていいか分からない…」
「出席日数が少なくて進路が心配…」
「本人が塾や家庭教師を嫌がる…」
サブスタなら、不登校中のお勉強の悩みを解決できます!
サブスタは無学年式のオンライン教材を、プロが作成する学習計画にそって進めていく新世代の勉強法です。
自宅で行えば「出席扱い」にもなるため、内申点対策や自己肯定感UPにもつながります。
14日間の無料体験ができる機会も用意しておりますので、ぜひこの機会にお試しください!

