
2011年、家庭教師派遣事業を展開する教育系グループの営業責任者に就任し、3年間従事。2015年に教育ベンチャーを起業して以来、一貫して小・中学生向けICT教材の企画・開発に携わり、無学年式のオンライン学習教材「サブスタ」を開発。
また、昨今不登校生が増え続ける中、全国の通信制高校と連携し、サブスタを通じて出席扱い制度普及の活動を行っている。

正しく学ぶ方法や成績の伸ばし方、
不登校に悩まれている方のための
情報を発信しています。
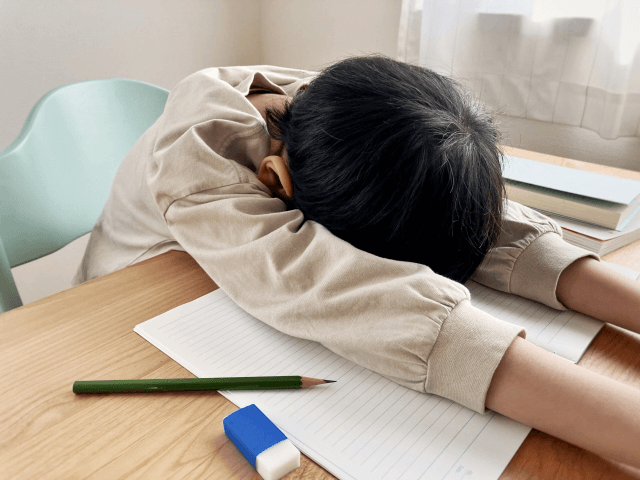
お子さまが不登校なってしまい、勉強しない様子を見ると将来に影響がでないか不安になる保護者様は多いのではないでしょうか。
「これ以上休むと勉強に追いつけない」
「このままだと取り残されてしまうかも」
数日だけならすぐに授業に追いつけますが、半年、1年と長くなるほど不安になるものです。
そこでこの記事では、お子さまが勉強しないと悩んでいる保護者様のために、どうして不登校になると勉強しないのか、親としてどのように対応していけばいいのか解説していきます。

不登校になってから勉強しないお子さまを見ていると、親の立場としては子どもの将来が心配でどうしたらいいのか悩んでしまいます。
結論から言うと、勉強に対する意欲がないうちは無理に勉強する必要はありません。
ここでは、勉強しないお子さまの姿を見ても悩まないように、勉強しない心理を解説していきます。
不登校になりはじめのころは、心も身体も非常に疲れている状態です。保護者様にとってはある日突然学校へ行かなくなったように思うかもしれません。しかし、お子さまにとっては、長い時間をかけて溜まったストレスが、限界に達して動けなくなったのです。
ですので、疲れきって精神的にも余裕がなく、勉強する気力など残っていません。保護者様が勉強するように追い詰めてしまうと、ますますお子さまのエネルギーはなくなっていきます。
心と身体が少しずつ元気になってエネルギーが貯まってくると、学校の勉強がどれくらい進んでいるか気になるお子さまもいるでしょう。休んでいる間に、学校の授業は進んでいます。数学や英語のように積み上げが必要な科目は、すぐには追いつけないと焦ってしまうかもしれません。
何から手をつけたらいいのかわからない、学校の勉強に追いつくためにどうやって進めたらいいのかがわからない、という状態になっている可能性もあります。
また、そもそも不登校になる前から、授業についていけず勉強嫌いのお子さまは、勉強の仕方そのものがわからない状況でもあるでしょう。
人間の脳は現状維持に安心して変化を嫌う性質があります。心理学では「現状維持バイアス」といい、変化することで起こるデメリットを避けるため、無意識で現状を変えない脳の働きをいいます。
不登校が続くと「とりあえずこのままでいよう」「登校してもまた嫌な思いをするに違いない」と脳内で現状維持バイアスが働き、リスクを回避しているのです。
このような脳の働きがあるため、不登校から動き出すにはかなりの勇気とエネルギーが必要なのがわかります。
不登校のお子さまは、心の中では勉強の遅れや将来のことを不安に感じています。しかし、毎日の授業や宿題になんの意味があるのか、勉強する意味もわからないお子さまも多いのではないでしょうか。
学校にいるとあたりまえのように勉強しているかもしれませんが、不登校になると勉強する意味や目的がなければ勉強する気にはなれません。

学校だけが勉強する場所ではなく、学校以外でも勉強できる方法はあります。生きていくうえで科目勉強だけが大切なのではありません。
「学校で勉強するのはあたりまえ」という保護者様の価値観が、不登校はよくないものだと位置付けをしているのです。
ここからは、学校で勉強しなくても心配や不安が小さくなる考え方や方法をお伝えします。
学校の成績はほとんどがテストの点数で決まります。ですが、テストの点数だけで人間の価値が決まるわけではありません。そもそも、ひとりの人間を点数で評価することはできないのです。
しかし、学校では成績が基準になり、周りと比べて自分の点数が悪いと人間的にも劣っていると自己否定してしまいます。保護者様は、お子さまの成績に一喜一憂せず、勉強だけの評価ではなくお子さまのいいところに意識を向けましょう。
学校へ行くことがあたりまえの考え方だと、不登校はダメな行為になります。しかし、すでに不登校になっているお子さまに「あたりまえ」を押し付けても意味がありません。
グローバル化が進み発展し続けている時代に、日本の教育システムは長い期間ほぼ変化がないと言われています。生きる環境がどんどん変化しているのに、進化しない学校の教育システムが合わない子どもがいても不思議ではありません。
学校へ行かなくても、学習を続けられる方法はあります。エネルギーが貯まり元気になってきたお子さまは、学校へ戻ることを考えているかもしれません。あるいは、学校へ戻らず自分がやりたいことを学べる場所を探しているのかもしれません。
保護者様は、お子さまの勉強する意欲が見られたら、どのような方法で学習が続けられるのかを一緒に考えてみてはどうでしょうか。

不登校でも「子どもに勉強させなければ」と焦る必要はありません。お子さまの勉強する意欲が出てきたら、遅れはすぐに取り戻せます。
しかし、親の立場で見守っていると、ついつい口出ししたくなるのではないでしょうか。ここからは、保護者様が勉強しないお子さまに対して意識しておくべきことをお伝えします。
不登校のうえ反抗期や思春期に入ったお子さまに「勉強しなさい」は逆効果です。勉強する意味や目的が見つかれば、自主的にはじめるので焦らずに見守りましょう。
小学校高学年や中学生になると、「勉強した方がいい」と説得しても反抗するだけです。余計な口出しはせず、お子さまの主体性が出てくるまで待つことが大切です。
お子さまに勉強して欲しいと思うのは、保護者様が安心したいからではありませんか。学校へ行かなくても、せめて勉強はして欲しいと思っていませんか。
学校へ行くか行かないか、勉強するかしないかは、お子さまの課題です。親のために学校へ行くのではなく、親のために勉強するのではないのです。不登校は親子ともども辛い経験ではありますが、お子さまが自分で乗り終えて人生を切りひらいていくしかありません。
保護者様は、お子さまのことをなんとかしてあげようとするのではなく、お子さまが助けを求めてきたときに全力でサポートしてあげてください。
前向きになってきたお子さまが、学校復帰に向けて勉強の遅れを取り戻す方法は以下の記事で詳しく解説しています。
▶ 不登校中の勉強遅れを取り戻す方法は?追い付くために親ができるサポート法も解説!
お子さまが不登校になると、学校へ行っている同級生と比べて悲観的になっていませんか。「勉強に追いつけない」「取り残されてしまう」このような不安が押し寄せてきますよね。
また「子どもが不登校なんて母親失格」と自分を責めていませんか。
このような感情は、他人と自分を比較して生まれてくるものです。他人を意識しすぎるあまり、自分で勝手な思い込みをしているにすぎないのです。
ネガティブな感情が出てきたら、自分の好きなことに没頭したりリフレッシュする時間を意識して作るようにしましょう。
勉強が遅れていたり、しばらく止まっていると不安になりものです。以下の記事では、不登校中の勉強法について解説していますので参考にしてみてください。
▶ 不登校中の勉強法はどうしたらいい?自主学習で遅れは挽回する方法を解説します

不登校期間中は、対面での指導や集団の環境に足を運ぶことが難しいお子さまいらっしゃるので、本人の状況に合った勉強方法を見つける必要があります。
ここでは不登校生で利用できる5つの勉強方法について解説します。
それぞれメリット・デメリットがありますので、お子さまの気持ちや予算に合わせて合っている方法を見つけましょう。
オンライン学習はインターネット上で配信されるオンライン教材やサービスを利用した新しい学習方法です。通信教育と呼ばれる、自宅へテキストが届き郵送でのやりとりを行う従来の「通信教育」から、現代ではスマホで簡単に利用できるものが増えています。
オンライン学習のサブスタでは、1000本以上の解説動画が24時間見放題で、個別指導塾と同等の学習をご自宅で手軽に行うことができます。決められた時間に通わないといけない塾と違い、不登校で生活のリズムがくずれていても、自分の好きなタイミングで学習できるのも合っているポイントです。
担当の学習アドバイザーがつくものの、学習指導は全て映像で行うので利用料金が低価格なのも特長になります。
また、不登校中でも出席扱いになる制度の利用をサポートを受けることが可能です。
不登校中のお子さまが中学生の場合、高校進学を見据えた出席日数の確保というのは悩みの種かと思います。しかし、不登校中でも学校出席扱いとなる場合がある、フリースクールや教育支援センター(適応指導教室)への通所は、集団の場に通うことが難しいお子さまにとってハードルが高いと思います。
そんなとき、不登校中でも出席扱いになる制度を取り扱っている通信教育サービスであれば、お子さまの勉強法の選択肢を広げることが可能になります。
家庭教師は、自宅に教師を招いて一対一で指導をしてもらう勉強法です。最近では、オンラインによる指導を実施しているところが増えています。オンライン学習は、自由度が高い分、継続にはお子さまのモチベーションが問われますよね。
しかし、家庭教師であれば指導を受ける時間は、半強制的に勉強に向き合うことになります。
また、いずれ学校復帰を目指す上で、家族以外の人とかかわりを持ち、信頼関係を築くという経験はお子さまにとってきっとプラスになるはず。保護者様にとっても、勉強のプロにお任せすることで安心を得られる部分もあるかと思います。
不登校中の学習対策として家庭教師を検討されている方は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
▶ 不登校向け家庭教師おすすめ10選!理解のある家庭教師を選ぶポイントを解説します
自宅ではモチベーションが保ちにくい、外出する機会がほしいといった場合、塾も有効な勉強法の1つです。かかる費用は、通塾の日数や指導してもらう教科の数によって異なります。
個別指導塾の場合は、お子さまのペースに合わせて講師が指導してくれますし、分からない問題があった際も他生徒に遠慮することなく質問することができます。
反対に、集団指導塾の場合は、塾の授業がは学校の授業進度などに合わせて一斉に進んでしまうため、お子さまの習熟度に合わない可能性があります。長期間の不登校によって勉強の遅れが気になる場合は、個別指導から始めた方が負担を感じることなく勉強できるでしょう。
不登校中の学習対策として塾を検討されている方は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
▶ 不登校生におすすめの塾10選!塾選びのポイントと5つのメリットを解説
フリースクールは、不登校などの事情により通学が難しいお子さまのための居場所となる民間施設です。必要な費用は施設によって異なりますが、決して安くない場合がほとんどです。
施設の運営方針は様々ですが、「勉強」を行う場所というよりはお子さまにとって以後心地の良い学校に代わる「居場所」がメインとなります。
お子さまに合った自由度の高いプログラムで学習できるほか、社会見学など勉強以外の体験ができるのは魅力的。同年代のお子さまが複数在籍しているため、少しずつ集団の場に慣れる練習の機会としても役立ちます。
また、決まった時間に出席したり規則正しい生活をしたりすることは、いずれ学校復帰を目指す上で重要となってきます。さらに、フリースクール通所を学校の出席扱いになるようサポートの体制が整っている場所もあります。
フリースクールについては下記の記事で詳しく解説していますので、興味のある方は参考にしてください。
▶ フリースクールとは?学校以外の学びの場をわかりやすく簡単に解説します!
教育支援センターは(適応指導教室)は、主に不登校のお子さまのために市町村の教育委員会が設置・運営している教育機関です。公的機関であるため、費用は無料もしくは少額となっています。
学習以外にも集団でさまざまな活動ができるという点はフリースクールと似ていますが、公的機関であるため市町村の学校との連携が密であり、通所が学校出席扱いとなるケースがほとんどという特徴を持っています。
しかし、教育支援センターの方針によっては学校への復帰を強く促されるケースもあり、不登校中のお子さまによってはプレッシャーとなってしまうことも少なくありませんので注意が必要です。
教育支援センターについては、以下の記事でくわしく解説していますので参考にしてください。
▶ 教育支援センターと適応指導教室の違いは?文部科学省の情報をもとに解説!
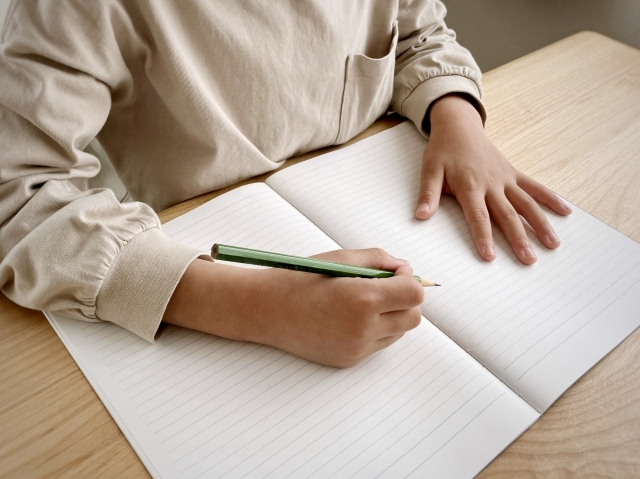
この記事では、不登校のお子さまが勉強しないのはどうしてかを解説するとともに、保護者様が意識しておくべきことについてもお伝えしました。ぜひ、参考にしてください。

こんなお悩みありませんか?
サブスタなら、不登校中のお勉強の悩みを解決できます!
サブスタは無学年式のオンライン教材を、プロが作成する学習計画にそって進めていく新世代の勉強法です。
自宅で行えば「出席扱い」にもなるため、内申点対策や自己肯定感UPにもつながります。
14日間の無料体験ができる機会も用意しておりますので、ぜひこの機会にお試しください!

