
2011年、家庭教師派遣事業を展開する教育系グループの営業責任者に就任し、3年間従事。2015年に教育ベンチャーを起業して以来、一貫して小・中学生向けICT教材の企画・開発に携わり、無学年式のオンライン学習教材「サブスタ」を開発。
また、昨今不登校生が増え続ける中、全国の通信制高校と連携し、サブスタを通じて出席扱い制度普及の活動を行っている。

正しく学ぶ方法や成績の伸ばし方、
不登校に悩まれている方のための
情報を発信しています。
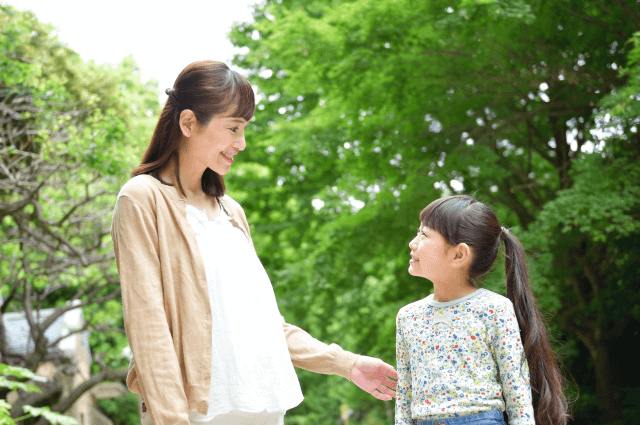
お子さまが不登校になると「母親が原因だ」「親のせいだ」という世間からの心ない言葉を耳にすることがあるかもしれません。しかし、不登校の原因が母親にあると決めつけることは適切ではありません。
とはいえ、不登校になるお子さまや不登校のお子さまをもつ保護者様にはいくつかの特徴がみられることも事実です。
今回は、不登校は母親が原因だといわれる背景や、不登校になるお子さまの特徴など幅広く解説していきます。
もくじ

お子さまが不登校になったとき、「その原因は母親にある」と断定することはできません。
それは、そもそも不登校はいくつもの要因が複雑に絡まりあって起こるものであり、原因を一つに特定することが難しいものだからです。また次項で解説するように、不登校の子どもを持つ母親には共通した特徴があると言われていますが、その特徴はどの保護者様も多かれ少なかれ持っているものといえます。
したがって、不登校の原因を母親と決めつけることはできません。
しかしながら、お子さまが不登校になると「原因は母親だ」「母親の教育不足だ」といった心ない言葉を耳にすることがあるかもしれません。
このような言葉は何を根拠に、どうして発せられるのか、世間が持つ“子育て”への根強いイメージをもとにご紹介します。
不登校の原因が母親であるといわれる理由の1つ目は、社会の中に「育児子育ては母親の役割」という考え方が根強く残っているためだと考えられます。
近年では共働き家庭が増え、男性も育児休暇を取得しながら積極的に子育てに関わろうとする動きが盛んですよね。しかしながら、まだまだ女性の家事育児負担が多いのは事実であり、子育てをメインで担うのは母親だという風潮は残っています。
そうした中でお子さまの不登校といった重大な出来事・トラブルが発生すると、その責任の所在は「子育てをメインで担ってきた母親にある」と考えられてしまうのです。
不登校の原因が母親であるといわれる理由の2つ目は、母親の存在がお子さまの性格形成に影響を与えるためです。
お子さまが不登校になるにあたっては、お子さま自身の性格も少なからず関係しています。たとえば、自己肯定感の低いお子さまは成績不振や友人との些細なトラブルに躓きやすく、自己肯定感の高いお子さまに比べて不登校になってしまう確率が高いといえます。
そして、このお子さまの性格というのは、生まれ持った気質と育った環境(育てられた環境)によって形成されるもの。小さなときからの保護者様のかかわり一つ一つが積み重なって、お子さまの性格は出来上がっていきます。
つまり、お子さまが不登校になりやすい性格である場合、その性格形成に関わった母親にも原因があるとされ、「不登校は母親が原因」といわれるのです。
しかしこの考え方はやや飛躍しすぎており、上記の理由①同様、子育ての責任を母親だけに押し付けているに過ぎません。子どもの性格形成に保護者様が影響を与えるというならば、その責任は父親にも同等に課せられます。
「父親が原因」との意見をあまり耳にしないあたりに、日本の子育ての風潮や歪みが感じられるともいえるでしょう。

「不登校は母親の責任」という心にもない意見を耳にすることはないでしょうか。そのような意見の発端は、不登校のきっかけに“お子さまの性格”も関係しているためだと思われます。
性格というのは、お子さまが生まれ持った気質と育った環境によって形成されていくもの。この“育った環境”の中で、お母様の存在は圧倒的であるため「不登校は母親の責任」という考えが浮かび上がるのです。
とはいえ、実際の不登校はさまざまな要因が複雑に絡み合って起こることが多いため、不登校の原因を一概に「母親のせい」と決めつけてしまうのは好ましくありません。
不登校のきっかけに「お子さまの性格」が影響していることや、そのようなお子さまを育てるお母様には一定の傾向があるのも事実です。
ここでは、不登校のお子さまをもつお母様の特徴について取り上げるとともに、そのようなお母様の特徴がお子さまに与える影響についてご紹介します。
不登校のお子さまをもつお母様に多く共通する特徴の1つ目は、過干渉かつ過保護であるということです。お母様が我が子にたっぷりと愛情を注ぎ、苦労なく育ってほしいと願うことは自然なことでしょう。
しかし、不登校のお子さまをもつお母様は、この思いが強すぎたり、子どもが苦労を味わわずに済むような先回り対策が手厚すぎたりするのが特徴です。本当ならお子さまが自分の力で達成できることでもお母様がやってしまう、なんてケースも多々あります。
このようなお母様のもとで育ったお子さまは、傷つくことに人一倍弱かったり、物事を自分で見通して判断・決断することが苦手だったりします。また、会話のスキルが乏しいのも特徴です。なぜなら、悩んだときに自分で解決しなくてもお母様が決めてくれるし、要望をうまく言えなくてもお母様が先回りして汲み取ってくれるから。
しかし、この人任せとも思える特徴は、子ども同士の関係ではなかなか通用しません。自分の意見をうまく伝えられないと、他者との仲も深まりにくいですよね。このように友人付き合いでつまづくと、学校への登校を億劫に感じてしまうようになる場合があります。
不登校のお子さまをもつお母様の特徴2つ目は、放任主義であるということです。前項の過保護・過干渉という特徴とは真逆ですよね。
放任主義のお母様の中には、「自分が子どもを放任している」という自覚はあまりなく、むしろ最近の流行りとも言える“叱らない育児”にのっとって「子どもの主体性を育んでいるのだ」と考えている方もいます。
しかし、“なんでも子どものしたいようにさせる”、“適切な場面で叱らない”というのは、裏を返せば“子どもに興味がない”とも見えますよね。周囲の反感を招くこともあります。
また、お母様に興味を抱かれず育ったお子さまは、愛情不足を感じていたり自分に自信が持てなかったり(自己肯定感が低い)します。繊細で、自分の行動に自信を持てないことが不登校へと繋がることもあるのです。
不登校のお子さまをもつお母様の特徴3つ目は、お子さまを管理しすぎる傾向にあるということです。前項の過干渉と少し似ている部分もありますよね。
お子さまを管理しすぎるお母様は、お子さまに対して「こうなってほしい」「こうであるべき」といったこだわりを強く持っており、価値観を押しつけ気味な面があります。
たとえば、人を管理したり、指導したりする職業(教師など)に就いているお母様が、家庭でもお子さまにもそのように接してしまう、というケースもあります。
しかし、管理されすぎたお子さまは、自分の力で問題を解決したり物事に柔軟に対応したりする機会が失われてしまいます。さらに、行き過ぎた管理がお子さまのストレスになることも…。
お子さまにとってお母様が安心して相談できる相手ではなかった場合、不登校の原因となっている悩みなどを上手く相談できず、問題が深刻化することもあります。
不登校のお子さまをもつお母様の特徴4つ目は、お子さまに対して批判的で感情的に怒ってしまうということです。
たとえば、お子さまのテストの点数が悪かったとき、そのような結果となった背景を読み取ろうとせず、単に点数が悪かったことについて感情のままに責めるのは好ましくありません。それについても注意は必要ですが、もっと気を付けなければならないのは「こんな点数をとるあなたはありえない」などといったように、お子さまの人格を否定することです。
お母様に批判され続けたお子さまは、自分の言動に自信が持てず、自己肯定感が下がってしまいます。自己肯定感が低いと、ちょっとした問題で大きく躓いてしまうこともあり、学校から足が遠のいてしまうケースもあります。
不登校のお子さまをもつお母様の特徴5つ目は、プライドが高いということです。世間体を気にしがちで、お子さまの失敗を自分の恥のように感じてしまうお母様もいます。
自分が劣等感を抱かなくて済むようにと、お子さまに少し背伸びをさせ、発達に合っていないことでも無理強いしてしまう、といったケースもあります。このように、お子さまに合っていないことを強要してしまうと、お子さまにとって家庭が安らげる場所ではなくなってしまいます。
また、過度に他人と比べられたことで自信がなくなり、学校で友達と関わることに恐怖を感じてしまう場合もあります。

では、上記のように不登校の原因になりやすい特徴をもつ保護者様に育てられたお子さまは、どのように成長するのでしょうか。
不登校になりやすい子となりにくい子では、いくつかの能力や特徴に差があるとされています。
ここでは、不登校になる子・なりやすい子がもつ特徴について詳しくご紹介します。
不登校になりやすいお子さまは、自己解決能力が乏しいことが特徴です。
これは、保護者様の過保護・過干渉や、管理的すぎる育て方が原因として挙げられます。前項でも少し触れましたが、保護者様のお子さまを守ろうとする行動が過度になると、お子さまが自分で考えてトラブルを解決する機会を奪ってしまうことになります。
困ったら保護者様が解決してくれる、保護者様の言う通りにすればよいという考えが沁みつくと、自分では何も解決できなくなってしまいますよね。このように育つと、学校でトラブル解決を自力で試みることもなく、解決できない=登校できないという結論にたどり着いてしまうことがあります。
過保護・過干渉気味な保護者様は、お子さまが失敗したりトラブルに巻き込まれたりすることから過度に守ろうとする傾向があります。そのような環境で育ったお子さまは失敗することへのハードルが高くなってしまいます。失敗するのではないかと心配するあまり、物事へチャレンジする意欲が消失してしまうのも自然なことですよね。
心配性によって学校でのトラブルも立ち向かうことなく「登校しない」という形で回避してしまうことがあります。
家庭内でお子さまが自分の意見を自分の口で発言する機会が乏しいと、コミュニケーション能力が低下する恐れがあります。
たとえば、過保護・過干渉な保護者様が先回りして行動しすぎると、お子さまは自分の口で要求を伝える必要がありません。また、日頃から保護者様がお子さまに批判的である場合、お子さまは自分の意見を口にすることに恐怖心を抱いてしまいます。
このようにコミュニケーション能力が適切に育まれないまま友人付き合いが始まると、そこで躓き、不登校のきっかけとなってしまうことがあります。
保護者様の過保護が行き過ぎていたり過剰に褒めたりする子育てをしている場合、お子さまのプライドが高くなってしまう可能性があります。
それは、家族の中で常に守られ最優先の扱いを受けてきたことから生じるものです。自分に自信がつくのはよいことですが、友人関係の中で折れることができなかったり自慢話が多かったりすると、煙たがられてしまいます。
管理的な保護者様のもとで育ったお子さまは、嘘や言い訳が多い傾向にあるといわれています。
それは、保護者様がお子さまに完璧を求め、失敗を許さない環境にあることが影響しています。保護者様からの叱責を避けるために嘘や言い訳で失敗を誤魔化してしまうのです。
しかし、そのような回避方法が習慣化すると友人からの信頼も得られにくくなってしまいます。
批判的、放任主義な保護者様のもとで育ったお子さまは、愛情に飢えてしまいます。そしてその心の隙間を満たし、どうにかして保護者様に認められようと承認欲求が高まっていきます。
次第にその欲求が家族以外にも向けられるようになると、過度に友人に依存してしまうなど、トラブルが起きやすくなります。
友人関係のトラブルは不登校のきっかけとなりやすいため、注意が必要です。

保護者様が、「不登校の原因は自分にあるのかもしれない」と感じたときにできる対応・するべき対応は何でしょうか。
ここでは、不登校の原因を自覚し、お子さまのために改善を試みる保護者様に向けた対応について解説します。
不登校の原因が保護者様(特にお母様)にある場合、まずはその事実を受け止め、保護者様にある問題を受け入れることから始めましょう。
不登校を改善させるためには、保護者様にある問題を適切に理解し、整理することが大切です。これまでの人生で培われた価値観を変えることは容易ではありませんが、お子さまの今後のためには保護者様自身の自己理解が必要となります。
保護者様自身の問題を受け入れることができたとしても、自分自身を責めすぎる必要はありません。保護者様もまた一人の人間ですし、保護者様が前に進むことができないとお子さまも先には進めません。
お子さまに加え、保護者様も塞ぎ込んでしまうというケースは避けたいものです。
保護者様自身の問題が自覚できたら、今一度お子さまと会話の機会を多く設けましょう。今までは保護者様の価値観の中でお子さまの話を理解していたかもしれませんが、問題を受け入れることでまた違った角度からお子さまの話を聞き、解釈できる可能性があります。
また、これまで見えていなかったお子さまの本心に気づけることもあるでしょう。
保護者様にある問題を明確化したり改善したりするために、学校の先生、カウンセラー、精神科医といった第三者に相談することをおすすめします。
そもそも、不登校を親子だけで解決するのは難しいですし、煮詰まってしまうこともあります。保護者様にある問題の有無にかかわらず、適切な専門機関を利用することが不登校改善への近道といえます。

不登校は、親のせいではありません。というのも、不登校の背景にはさまざまな要因が存在するため、それを「親のせい」と決めつけてしまうのは相応しくないのです。
とはいえ、不登校のお子さまを持つ保護者様がご自身を責めてしまうのは自然なことでしょう。しかし、保護者様が「不登校は親のせいだ」とご自身を責めすぎてしまうと事態は悪化しやすくなります。
ここでは、不登校が親のせいであると感じない、感じすぎないための心構えについてご紹介します。
お子さまが不登校になると、しばしば周囲から「親のせいだ」「親の教育がきちんとしていないからだ」と言われることがあります。
たしかに、お子さまの性格が原因で不登校になっている場合、その性格が形成される背景には「保護者様との関わり」があるため、一概に保護者様と不登校の関連を否定することはできないかもしれません。
実際、不登校になりやすいお子さまの保護者様にはいくつかの特徴があることが報告されています。
しかし、お子さまが不登校になる原因は実に複雑です。いじめ、お子さまの気質によるもの、学力、無気力など、挙げればキリがありません。不登校の背景には、人間関係や家庭環境をはじめ、お子さま自身の問題などが複雑に絡み合っているのです。
ですから、「不登校は親のせい」と決めつけてしまうのはあまりにも短絡的とも言えます。不登校の原因は複雑であることを認識し、保護者様がご自身を責めることがないようにしましょう。
不登校の具体的な原因については、以下の記事でさらに詳しくご紹介しています。
▶不登校になる原因は?文科省の情報から増加の背景や対応法を解説!
お子さまは、保護者様が思う以上に保護者様の思いを理解しています。上記でご紹介したように保護者様が「不登校は親のせい」だと感じ、ご自身を責めると、それは自然とお子さまにも伝わることでしょう。
保護者様が自分を責める様子は、お子さまのストレスになってしまいます。また、不登校になったことへの罪悪感から自分に自信が持てなくなったり、登校再開がより難しくなったりしてしまうこともあります。
不登校になっても保護者様が「親のせい」と感じすぎず、保護者様自身の人生を大切にすることも重要です。
お子さまの不登校の対応で疲れやストレスを感じている保護者様向けに、気持ちが楽になる方法を以下の記事で解説していますので参考にしてください。
▶不登校の子どもを持つ親はしんどい!疲れた気持ちが楽になる方法とは?
不登校になると、ついお子さまの不登校後の生活や将来について心配してしまいますよね。欠席が続くと、今後の人生に差し支えるのではないかと懸念する保護者様もおられるでしょう。
しかし極論にはなりますが、小学校・中学校という義務教育期間中は留年の心配はありません。
「焦らなくても卒業はできる」
そう思うだけで少し心が楽になることもあります。また、学習面に関して言えば、サブスタなどの教材を利用して自宅で勉強することも可能です。不登校でも、さまざまな支援やサービスを利用することで補える面はたくさんあります。
保護者様が焦りすぎず、寛容な姿勢で不登校を受け止められるとよいですね。
不登校でも自宅でオンライン学習を行うことで出席扱いが認められることがあります。不登校生の出席扱い制度については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
▶不登校生が出席扱い制度を利用すると内申点はどうなる?メリットについて徹底解説します!
前項でご紹介したように、義務教育期間に関しては不登校であっても進級・卒業が可能です。しかし中学校卒業後の進路は自分で決めなくてはいけません。
多くの不登校のお子さま・保護者様を悩ませるのは、この高校進学問題です。
中学校卒業後には、就職、進学などいくつかの進路の選択肢があります。
高校と一口に言っても、全日制、定時制、通信制など種類はさまざまです。不登校であっても卒業後の行き先はある、お子さまに合った進路を選ぶことができると分かっているだけでも安心できますよね。
親子でしっかりと話し合い、卒業後の進路についてお子さまの考えが理解できていることが大切です。
進路選択までに時間の余裕がある場合は、資料を取り寄せたり、実際に学校を見学してみることをおすすめします。卒業後の進路を具体的にイメージできることで、そのためには何をやっておけばいいのか明確にできますよね。
進路について漠然とした不安を抱えるのではなく、今やるべきことを具体的に知ることで、不登校のストレスが緩和されることもあります。
不登校のお子さまの進路やその後については、以下の記事でさらに詳しくご紹介しています。
▶不登校経験者はその後どうなる? データをもとに不登校経験後の進路をご紹介

不登校の原因が親のせいではなくても、何か親としてできることはないだろうかと保護者様は思われることでしょう。
保護者様はなにも特別なことをする必要はなく、お子さまに寄り添い信頼関係を築くことが重要です。
ここでは、保護者様にできる“親のせいではない不登校”への対応についてご紹介します。対応子どもとの会話を意識する
前項でも少し触れましたが、まずはお子さまとの会話の機会をしっかりと確保しましょう。その際、無理に学校の話題を話したり不登校の原因を探ったりする必要はありません。まずはお子さまの好きなこと、盛り上がれる内容であればなんでもよいのです。不登校に至るほど疲れた心を休息させることが先決です。
不登校について問い詰められない、他愛のない話ができる、という状況はお子さまにとって居心地のよいものです。不登校の原因については、そういった親子関係の中で安心感を得ることで自然と話し出すケースが多々あります。
原因が分かれば、保護者様も「親のせい」の自分を責める必要がなくなるでしょう。
お子さまとの会話や信頼関係の構築と並行してやるべき重要なことは、「不登校を理解する」ということです。学校に行けないお子さまをただただ見守るだけでは、保護者様は焦り葛藤してしまうばかりですよね。
しかし、不登校という現象について知見を得ることで、お子さまの現状をより深く理解できます。「不登校の背景にはお子さま本人の気質的なものもあるかもしれない」、「発達障がいの可能性は?」、「朝起きられなくて登校できないと言うけど、実は病気かも?」といったように、さまざまな可能性を考えることができます。
それを知らず、お子さまを叱責してしまっては信頼関係を築くこともできません。
不登校の情報を収集する中でお子さまの現状と照らし合わせ、理解を深められるとよいですね。
不登校の法的な定義に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
▶不登校の定義は欠席何日?最新の法律をもとに定義や実態を紹介します
不登校で悩んだときの相談先を知っておくと、いざというときに安心です。
お子さまの相談はもちろんですが、保護者様の不安な心情を専門家に聞いてもらえると心強いですよね。家庭内に閉じこもり、親子だけで過ごす生活はお互い自然とストレスも溜まっていきます。そのようなとき、第三者に話を聞いてもらうことがよい息抜きとなる場合もあります。
相談先は、学校のスクールカウンセラーをはじめ、カウンセリング施設、児童相談所、医療機関など多岐にわたります。悩んだときに頼れる先があることが親子ともに心の余裕へと繋がります。

ここまで、不登校のお子さまをもつお母様の特徴をご紹介してきました。
これらを読んで、「不登校の原因は親のせいだったのかも…」と気に病んでおられるお母様もいらっしゃるかもしれませんね。
しかし、程度の差はあれど、これらに全く当てはまらないお母様の方が珍しいのではないでしょうか?お子さまのためを思い、行動しているうちにいずれかの特徴に当てはまっていくことは自然とも言えます。
重要なのは、上記の特徴に当てはまりすぎていないかということです。
なかなか自分の特徴には自分で気づきにくいですし、これまでの人生の中で培われてきた価値観を変えるのは容易ではありません。
人生経験が長い分、お子さまの意識を変えるよりも難しいでしょう。しかし、少なからずその自覚があり危機感を抱いたからこそ、この記事を読んでくださったはずです。
まずはお母様が周囲のサポートを受けながら自身のお子さまとの関わり方を見つめ直すことが第一歩とも言えます。決してご自身だけを責めず、お子さまと向き合ってみてくださいね

こんなお悩みありませんか?
サブスタなら、不登校中のお勉強の悩みを解決できます!
サブスタは無学年式のオンライン教材を、プロが作成する学習計画にそって進めていく新世代の勉強法です。
自宅で行えば「出席扱い」にもなるため、内申点対策や自己肯定感UPにもつながります。
14日間の無料体験ができる機会も用意しておりますので、ぜひこの機会にお試しください!

