
2011年、家庭教師派遣事業を展開する教育系グループの営業責任者に就任し、3年間従事。2015年に教育ベンチャーを起業して以来、一貫して小・中学生向けICT教材の企画・開発に携わり、無学年式のオンライン学習教材「サブスタ」を開発。
また、昨今不登校生が増え続ける中、全国の通信制高校と連携し、サブスタを通じて出席扱い制度普及の活動を行っている。

正しく学ぶ方法や成績の伸ばし方、
不登校に悩まれている方のための
情報を発信しています。
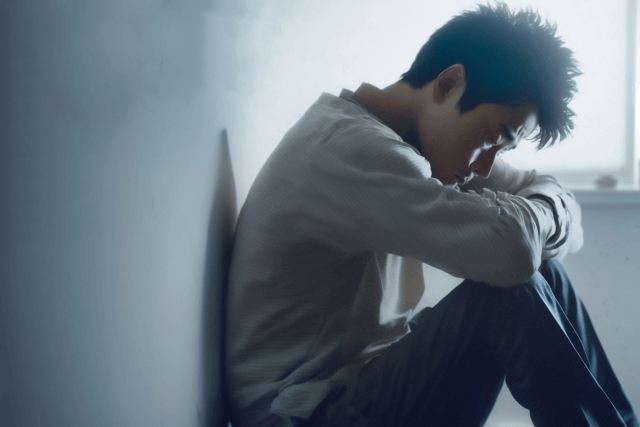
不登校になると、共通してよくみられる「あるある行動」があります。今までできていたことができなくなったり、話が通じなくなったり、お子さまの行動や考え方の変化が気になる保護者様も多いのではないでしょうか。
不登校の「あるある行動」には理由があります。理由がわかれば深刻に悩む必要はありません。この記事では、不登校のお子さまに共通した行動を、心の動きから解説していきます。
もくじ

お子さまが不登校になると、今までの規則正しい生活ができなくなります。特に不登校の最初の頃は、保護者様もお子さまの言動に振り回されて、辛い日々を過ごしているのではないでしょうか。ここでは、不登校になると陥りやすい言動を紹介します。
学校へ行く準備はするけれど、登校時間になると頭痛や腹痛などを訴えます。玄関に長時間座り込んだり、学校に着いてもなかなか教室には入れず、保健室へ行ったり帰宅するお子さまもいるでしょう。
保護者様が、お子さまの生活習慣でなんとかしたいと頭を悩ますのは、昼夜逆転ではないでしょうか。ゲームやネットを楽しんでいるうちに、いつの間にか朝になっていたというのはよくあることです。また、自律神経の働きの不調で朝起きることができず、徐々に家族と生活時間がずれていくことがあります。
不登校中に昼夜逆転してしまう現象については、以下の記事で詳しく解説しています。
▶不登校中の昼夜逆転はスマホのせい?治し方や原因を解説します!
不登校で無気力になると、お風呂に入らない、着替えない、歯を磨かない、など今まであたりまえにできていたことができなくなることがあります。
朝起きなかったり、運動もしていないので、学校へ行っているときに比べると食事をする時間や量はずいぶん変わるでしょう。保護者様は、不規則な食事と体力低下に不安になるかもしれません。
家にいると必然的にスマホやパソコンを使う時間が長くなります。ゲームやネットをしている時間は現実を忘れることができるので、夢中になるお子さまは少なくありません。
不登校中にゲームに没頭してしまう現象については、以下の記事で詳しく解説しています。
▶不登校中にゲームを禁止にしたら逆効果?取り上げなくても大丈夫な理由を解説
人目を気にするあまり昼間は外出せず、知っている人に会わない時間帯にコンビニへ行ったり出歩くことがあります。
うまく言語化することができず、保護者様に暴言を吐いたり、暴力を振るうことがあります。中学生になると身体も大きくなり力も強くなりますので、身の危険を感じる場合は第三者の助けが必要です。
不安な感情を言葉で表現できず、保護者様に甘えることがあります。また、甘えることを常に我慢してきたお子さまは、自己承認欲求を満たすために幼児退行する場合があります。
「学校へ行く」「勉強する」と発言しても、実際は身体が動かず実行しないお子さまは多いと思います。保護者様の不安や心配を察しての発言ですが、過度に期待をしてしまう保護者様は落胆することが多いのではないでしょうか。

保護者様は、「あるある行動」をするお子さまの心理がわからず、どのように対応すればいいか悩んでいませんか。不登校の「あるある行動」には理由があります。
ここでは、どうして「あるある行動」をするのか、お子さまの心の動きを知ってどのように対応すべきか解説していきます。
不登校の「あるある行動」の中で、朝の体調不良、昼夜逆転、お風呂に入らない、食生活の乱れ、など規則正しい生活を求める保護者様にとっては大きな悩みではないでしょうか。
しかし、生活を無理に正そうとするのは意味がありません。
なぜなら、ストレスや悩みを抱えて極限まで追い詰められたお子さまは、無意識に自分の命を守ろうとして動けなくなっている状態だからです。神経生理学の「ポリヴェーガル理論」によると、命の危機に直面すると自己防衛反応で不動化(フリーズ)し、シャットダウン、無気力状態になると言われています。
今までできていた規則正しいあたりまえの生活ができなくなるのは、不登校のお子さまにとって、命を守ること以外の重要なことではないからです。お子さまにとっては無意識の行動なので、理由は説明できません。
保護者様は、命を守ろうとする心理が働いていることを受け止めて、見守る姿勢でいることが大切です。
学校や家族にも理解してもらえず居場所がないお子さまは、ゲームやネットの世界へ逃避して、そこが唯一の居場所になっていると考えられます。保護者様は、感情的になってゲームを悪者にするのではなく、お子さまの居場所になっていると理解したうえで、ゲームとうまく付き合う方法を話し合うといいかもしれません。
また、夜に外出するのは、誰にも会いたくないという理由があります。普通の生活をしている人の目から逃げたいという心理が働いています。
お子さまが、家族と距離を置いたり人の目を気にしているときに、保護者様の価値観で正論を言うのは逆効果でしょう。現実逃避したい気持ちに共感しながら、家を安心安全の場所にすることが大切です。
保護者様が、現実逃避しているお子さまに不安や心配を持ち続けていると、いつまでも自分はダメな人間だと自己否定を緩めることができません。
ですので、お子さまが自分に自信を持てるようにするには、まず保護者様がありのままのお子さまを認めることです。
暴言暴力は、気持ちのコントロールができないときに起こります。
自分でもどうして学校へ行けないのかうまく説明できない、家族からは理解してもらえない、というストレスから感情が荒れて暴言暴力で吐き出しています。解って欲しいと訴える心の叫びを、暴言暴力でしか表せないのです。
保護者様は、受け入れなければと常に受け身でいる必要はありません。暴力に危険を感じる場合は、第三者の力を借りて身の安全を確保する必要があるでしょう。
しかし、お子さまを避け続けるのではなく、落ち着いた様子のときに、手紙を渡したりメールを送るなどの手段で、あなたの味方であると伝えることが大切です。
また、幼児退行するお子さまは、自分の気持ちを言葉で表現するのではなく、甘えるという行動で保護者様に伝えています。自分のことをどう思っているか確かめながら情緒を安定させているので、保護者様は拒否せず承認することが大切です。
このときにしっかり自己承認欲求を満たしてあげることで、幼児返りは終わり心が元気になっていくはずです。
お子さまは、保護者様の顔色を見て、学校へ行かなければ、勉強しなければ、と思っています。保護者様を安心させようという心の動きがあります。
しかし、そうは言ってもほとんどの不登校のお子さまは実行できません。学校へいこう、勉強しようという気持ちはあるので、保護者様はできない結果を責めないように気をつけなければなりません。
お子さまは、できなかった結果を責められることで自己否定を強めていきます。保護者様の、学校へ行ってほしい、勉強して欲しいと願う非言語を読み取って発言しているので、お子さまは無駄にエネルギーを使っていることにもなります。
学校へは行っても行かなくてもいい、勉強はしてもしなくてもいい、という姿勢でお子さまを見守りサポートすることが大切です。

今回は不登校によく見られる「あるある行動」について紹介しました。
「あるある行動」には理由があります。保護者様は、今までできていたことができなくなったと悲観せず、お子さまにどういう心の動きがあるかを知って、不登校の時期を見守りましょう。
不登校になったお子さまも、しばらく時間が経ち落ち着いてくると回復期に入ります。本記事で解説した「あるある行動」とは全くちがう特長が見られるので、併せて参考にしてください。
▶不登校の回復期はどのような特長がある?逆戻りも想定内な理由と親の接し方を解説

こんなお悩みありませんか?
「不登校が続いて勉強の遅れが心配…」
「勉強をどこから始めていいか分からない…」
「出席日数が少なくて進路が心配…」
「本人が塾や家庭教師を嫌がる…」
サブスタなら、不登校中のお勉強の悩みを解決できます!
サブスタは無学年式のオンライン教材を、プロが作成する学習計画にそって進めていく新世代の勉強法です。
自宅で行えば「出席扱い」にもなるため、内申点対策や自己肯定感UPにもつながります。
14日間の無料体験ができる機会も用意しておりますので、ぜひこの機会にお試しください!

